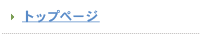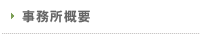ブログ


1 今回は、入管法改正に伴い、新たに導入された「みなし再入国許可制度」について解説していきます。
そもそも、「再入国許可制度」とはいったいどのような制度なのでしょうか。
2 再入国許可制度については、入管法26条において、「法務大臣は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続きにより、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。」と規定されています。
この規定だけでは、分かりにくいですが、要するに日本に在留する外国人が一時的に出国し、在留期間内に再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可のことを再入国許可といいます。
3 通常、外国人が新たに日本に入国しようとする際は、有効な旅券及び査証が必要となります。しかし、適法に在留している外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する場合にまで、新規に入国する場合と同様の手続きを課すのは、あまりに不合理です。そこで、再入国許可制度により、再入国の許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、新規入国者には、通常必要とされる査証が免除され(入管法6条1項但書)、簡便な上陸審査手続(入管法7条1項)により上陸許可を受けられることになっているわけです。
4 以上が、通常の「再入国許可制度」の簡単な説明ですが、新たに導入された「みなし再入国許可制度」のもとでは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。
ただし、次に掲げる外国人は、みなし再入国許可制度の対象となりません。
①在留資格取消手続中の者
②出国確認の留保対象者
③収容令書の発布を受けている者
④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格を持って在留する者
⑤日本国の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる理由があるとして法務大臣が認定する者
4 なお、みなし再入国許可制度を利用して出国した外国人が、出国後1年以内に再入国しない場合、在留資格が失われるので、注意が必要です。1年以内の再入国を予定している場合であっても、不測の事態が発生すれば1年以内に再入国できない可能性があるような場合には、通常の再入国許可を受けて出国するのが望ましいといえます。
(田中涼)
1 はじめに
「家族(友人、知人)が逮捕されたのですが、本人と面会できますか?差入れもしたいのですが、できますか?」
刑事事件でよくある質問です。これには、まず、逮捕された後の身体拘束手続きの流れの説明から始めなければなりません。
2 身体拘束手続きの流れ
⑴ 罪を犯したのではないかと疑われている人のことを「被疑者」と呼びます。テレビなどでは「〇〇容疑者」などと言われることがありますが、だいたい同じ意味です。
警察官が被疑者を逮捕した場合、留置の必要があると考えたときは、身体拘束した時点から48時間以内に、書類や証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続きをしなければなりません。警察の逮捕の手持ち時間は48時間だと言われる理由です。
警察官から送致された被疑者を受け取った検察官は、留置の必要があると考えたときは、被疑者を受け取った時点から24時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません。もっとも、検察官が手持ちの24時間の枠をギリギリ一杯使うということはあまりないように感じます。
このように、逮捕と呼ばれる段階は、警察官と検察官の手持ち時間合計72時間が最長という建前になっています。
⑵ 検察官が勾留請求すると、裁判官が、引き続き被疑者を拘束する理由があるか、必要性があるかを判断します。あると判断された場合は、被疑者は「勾留」され、勾留請求された日から10日間、引き続き拘束を受けます。
⑶ この10日間の内に、捜査機関が必要な捜査を終えることができないときは、検察官により、勾留の延長請求がなされる場合があり、裁判官がやむを得ない事由があると判断したときは、最長10日間延長されることがあります。
検察官は、原則として当初の勾留10日目までに、勾留延長があった場合は延長された期限までに被疑者を起訴するか否かの判断を迫られます。勾留中に被疑事実と同一事実で起訴すると、自動的に被疑者勾留が起訴後勾留に切り替わり、引き続き2か月間勾留されますが、起訴しない場合には被疑者を釈放しなければならないからです。
起訴後勾留は原則2か月とされていますが、一般的には2か月の期限が到来しても判決がなされるまでは1か月ごとに勾留が更新されますので、保釈されない限り判決まで身体拘束が続くことになります。
3 面会について
⑴ 被疑者の家族、友人知人も含めてですが、被疑者と面会(接見といいます。)をすることは基本的に可能です。ただし、それには、様々な制約があることに留意しなければなりません。
⑵ 刑事訴訟法80条は、次のように定めています。
「勾留されている被告人は、第三十九第一項に規定する者(※)以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」
※ここで出てくる「第三十九第一項に規定する者」というのは、弁護人又は弁護人となろうとする者(以下、「弁護人等」といいます。)のことで、端的に言えば弁護士のことです。ですので、この条文は、弁護士以外の人とも接見したり物品をやりとりすることができますよ、但しそれは法令の範囲内に限られますよ、ということが定められているということになります。なお、この条文は被告人、つまり起訴された後の勾留手続きに関するものではありますが、起訴前の被疑者段階の勾留手続きにも準用されます。
具体的には、次のような点に注意しなければなりません。
① 接見の申込が受け付けてもらえる時間は、あらかじめ決められています。平日午前9時半から11時半まで、午後1時から4時までなどとされているようですが、留置場所によっても違う可能性がありますので、接見前に電話などで問い合わせるとよいでしょう。留置場所は、被疑者の段階では基本的には警察署の留置場ですが、例外的に被疑者段階から拘置所に留置される場合もありますので注意が必要です。
② 回数制限、人数制限があります。被疑者1人につき、1日1回1組まで、1組3人までとされているようです。ですので、接見に行くと、その日に本人が別の人と既に接見を済ませていた場合は、その日はもう接見はできないということになります。接見に行く日がバッティングしないように、家族や友人どうしで連絡をとりあい、調整しておくことが望ましいですね。また、1組あたり3人までとされていますので、4人以上で面会を希望しても、一度に全員は面会室に入れてもらえません。
③ 時間制限があります。警察署の留置場では1回15分~20分とされているようですが、接見の混み具合等によって短縮される場合があります。
④ 取調べなどの捜査の都合により断られる場合があります。本人が取調べを受けている最中なので接見できない場合や、現場への引きあたり捜査で出かけているとか、勾留質問を受けるために裁判所に出かけている等の理由で、本人が留置場所に居ないので物理的に接見できないことがありえます。留置場所に居るかどうかは、留置場所に電話などで問い合わせると教えてくれる場合がありますので、聞いてみるとよいでしょう。
⑤ また、本人が接見したくないと言っている場合も接見できないことがあります。上記の1日の回数制限の関係で、その日に後で別の人に接見をする予定がある場合、その人との接見ができなくなると困るので、本人が断るということもあるようです。
⑶ もう一つ注意しなければならいことは、弁護人等以外の人との接見が、裁判官によって禁止されることがありうるということです。刑事訴訟法81条は次のように定めています。
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者(※)以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押さえることができる。」
これを接見禁止といいます。被疑者が当該被疑事実を否認していたり、共犯者がいるとされている事案、特に集団的に行われたとされる事案においては、裁判官がこの接見禁止命令をする場合が少なくありません。その場合には、弁護人等以外の家族、友人、知人は、接見することはできません。また、物品の授受をすることも禁止されるのが通常です。つまり、差入れ、宅下げ(差入れの反対に、被疑者が家族等に手持ちの物品を持ち帰ってもらうことを宅下げといいます。)が禁止されるということです。もっとも、衣類や書物、食べ物や生活必需品等の差し入れは通常禁止されませんので差入れることができます。
この接見禁止は、原則としては起訴されるまでですが、裁判官が必要と判断したときは、起訴後も更新される場合がありますので、起訴されたからといって必ず接見禁止が解けて接見できるわけではありません。
もしどうしても本人と連絡をとる必要がある場合には、弁護人等に連絡をとって、伝言を依頼するという方法があります。弁護人等以外の人の接見では、警察の係の人が接見室に同席しますので、会話の内容が知られてしまいますが、弁護人等は立会人 なしで接見することができますので、秘密を守ることができます。
(中野星知)
1 2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。これまでの在留管理制度と何がどう変わったのか、基本的な変更点について数回にわたり解説していきます。
今回は、新たな在留管理制度のもと、外国人に交付されることになった「在留カード」について述べたいと思います。
2 2012年7月9日以前の旧制度である外国人登録制度においては、日本在留の外国人は、原則として、日本に在留することとなった日から一定の期間内に、居住している市区町村に身分事項や居住地等を届け出て外国人登録をする必要がありました。
それ以外に、日本に上陸する時や、在留資格を更新する時などには、入管法に基づいた手続きが必要となり、それにより、入国管理官署に当該外国人の情報が把握されていたわけです。
このように、これまでは、入管法と外国人登録法という二元的な情報把握の体制がとられていました。
3 それが、新たな在留管理制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止され、法務大臣が在留資格をもって我が国に在留する外国人に在留カードを交付し、一元的に外国人の在留情報を把握する体制に改められたのです。
4 新たな在留管理制度の対象となる、つまり在留カードが交付されるのは、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人であり、①〜⑥のいずれにも該当しない人です(入管法19条の3)。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①〜③の外国人に準じる者として法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
5 在留カードは、対象となる外国人に対し、上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新許可等の在留に係る許可に伴って交付されます(入管法19条の6、20条4項、21条4項)。在留カードは、常時携帯する義務があり(入管法23条2項)、携帯義務違反に対して罰則も設けられていることから注意が必要です(入管法75条の3)。
6 在留カードには、写真が表示され(入管法19条の4第3項)、以下の事項が記載されます(入管法19条の4第1項)。
① 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法2条5号ロに規定する地域
② 住居地(本邦における主たる住居の所在地)
③ 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
④ 許可の種類及び年月日
⑤ 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
⑥ 就労制限の有無
⑦ 資格外活動許可を受けているときはその旨
6 次回は、新しい在留管理制度のもと導入されたみなし再入国許可制度について解説したいと思います。
1 標準契約書と原状回復ガイドライン
前回、賃貸住宅の退去時の原状回復、敷金返還をめぐるトラブルが増えているというお話をしました。主に、退去後の修理、クリーニング、リフォームなどの費用を、賃貸人と賃借人のいずれがどこまで負担するのか、その範囲と費用負担をめぐるトラブルです。
このような状況を受け、平成5年に旧建設省(現在の国土交通省)が「賃貸住宅標準契約書」を発表しました。これは、賃借人の居住の安定の確保と賃貸住宅の経営の安定を図る目的で、賃貸住宅の契約書のひな形として参考にされるようにと作成されたものです。そして、近時、国土交通省は、その改訂版を発表しています。
また、国土交通省は、平成16年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)も発表し、近時再改訂されました。これは、過去の裁判例や取引の実務を踏まえ、原状回復の費用負担のあり方などについて、トラブルを未然防止の観点から、現時点において妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてまとめたものです。
2 ガイドラインの概要
建物の価値は、人が居住するか否かに関わらず、時間が経過すれば減少するものであり、契約によって定められた使用方法に従い、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、それが使用開始当時の状態よりも悪い状態であったとしても、賃借人としてはそのままの状態で賃貸人に引き渡せば十分であるというのが、原状回復に関する支配的な考え方であると前回ご紹介したところです。しかし、具体的にどのような場合に、どこまでの範囲が賃借人の負担となるのかは、そのような一般的で抽象的な基準を言われただけでは何も分かりません。
この「ガイドライン」は、上記の基準よりももう少し具体化した一般的な考え方を示すとともに、さらに、原状回復をめぐってよく問題となる「畳、フローリング、カーペット」「壁や天井のクロス」「ふすま、柱」「その他の設備」などの項目別に、どのような場合に賃借人が費用を負担する必要があるのかの基準を示してくれていますので、大変参考になります。
3 ガイドラインの例
ガイドラインの中身を若干紹介しますと、
・ 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
(考え方)家具保有数が多いというわが国の実情に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。
・ タバコのヤニ
(考え方)喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲内であると考えられる。
などといった考え方が示されています。読んで少し意外な印象を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
4 ガイドラインの位置づけ
このガイドラインは、国土交通省が発表しているものではありますが、法的拘束力はありません。裁判規範性がありませんので、トラブルが訴訟に発展した際に、裁判官がこのガイドラインに従って判断しなかったからといって、その判決が違法ということにはなりません。
個別具体的な事案において、原状回復費用の賃貸人と賃借人間の負担の問題は、契約の内容や、物件の状況等によって、あくまで個別に判断されることになります。が、このガイドラインは、個別具体的な事案における解決のために、賃貸人賃借人間の交渉や、裁判になったときの判断の指針として利用されることが期待されています。そして、実際にも、このガイドラインはトラブル解決の指針として参照され、影響力を持っていると言えます。
(中野星知)
1 最近、円安が進行していることも影響し、今年4月に日本を訪れた外国人旅行客の数が90万人を超え、過去最多を記録したようです。
今回は、外国人が日本を訪れるために必要となるビザ(査証)について述べたいと思います。
2 外国人が日本に上陸するためには、原則として、有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに、旅券に有効な査証(ビザ)を取得していることが必要とされています。
査証とは、日本国領事館等が、外国人の所持する旅券は真正なものであって、入国目的からみて日本への入国は問題ないと判断されることを旅券に表示(査証印を押す)したものをいいます(黒木忠正『入管法・外登法用語辞典』75頁(日本加除出版、平成13年))。
日常会話では、「ビザを更新した。」といった具合に、「在留資格」のことを'ビザ'ということがままありますが、ここでいう査証(ビザ)とは異なる意味で使われていることにご注意下さい。
3 査証は、外国人が日本に到着後国内で取得することができないことから、事前に外国にある在外日本領事に対してビザ申請を行い、取得しなければなりません。査証はあくまで、日本国領事館等による入国審査官に対して、当該外国人の日本入国について問題がないとする推薦するものにすぎないので、有効な査証があれば、通常は上陸が許可されますが、査証を所持していても、入国の際に上陸拒否事由(入管法5条1項各号)が発覚するなどすれば、上陸が許可されないことがあるので注意が必要です。
4 ここまで読んで、「外国人が、日本に観光のために入国するような場合にも本当に査証(ビザ)必要なのかな?」と疑問に思った人もいるかもしれません。さきほど、「外国人が日本に上陸するためには、原則として、有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに、旅券に有効な査証(ビザ)を取得していることが必要」と述べたように、確かに査証(ビザ)が不要な場合もあります。
すなわち、査証免除取決め等により査証を要しないこととされている国の国民の旅券、再入国の許可を受けている者の旅券又は法務大臣から難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、査証が不要であることが入管法6条1項但書に規定されています。
日本においては、平成23年5月時点において、計61の国と地域との間で一般査証免除措置を実施しており(外務省HP http://www.mofa.go.jp参照)、これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して査証を取得する必要はありません。
(田中涼)
1 敷金返還と原状回復
法律相談などでも、賃貸借契約で賃借人が退去する際の原状回復をめぐるトラブルによく出会います。敷金返還の問題と原状回復の問題とは密接に関連しています。賃貸人は、賃借人からマンションの部屋などの明渡しを受けると、壊れた箇所を修理したり、壁紙を貼り替えるなどのリフォームをしたりして次の人に貸すための準備をします。それにかかる費用のうち、賃借人がどこまで負担しなければならないか、賃貸人はどこまで賃借人に請求することができるかによって、敷金の内いくらが賃借人に返還されるべきかが決まってくるからです。
2 原状回復義務とは
賃貸借契約が終了すると、賃借人は、賃借物を原状に復して返還しなければなりません。これを原状回復義務といいます。不動産の賃貸借では、契約書に「賃借人は、本物件を原状回復しなければならない。」などと明記されているのが通常です。
では、「原状に回復する」というのはどういうことを意味するのでしょうか。例えば、新築マンションを5年間賃借したという場合、賃借人は新築同然にして返還しなければならないのでしょうか。それとも、うっかり壊してしまったりした部分などを修理するだけでよいのでしょうか。
これについては、原状回復とは、契約書に特別な約定(特約)がない限り、入居した場合と全く同一の状態に戻すということを意味するわけではなく、経年劣化によって生じたり、通常の用法に従って使用していた場合に生じるような損耗・汚損(「通常損耗」といいます。)については、賃借人は元通りにする必要は無く、そのままの状態で賃貸人に引き渡せばよいと考えられています。
なぜかというと、そもそも賃貸借契約は、目的の物件を賃借人に使用させ、その対価として賃貸人は賃借人から賃料を受け取るのですから、通常のやり方で使用することによって生じる損耗や汚損は、賃借人が支払う賃料の中に既に織り込み済みだと言えるからです。
仮に、これとは逆に、借りた時と全く同一の状態にして返さなければならないのだとすると(上記の例でいうと、5年前の新築の状態にして返さなければならないのだとすると)、賃貸人はいつまでもそのマンションを新築の状態で保持しつつ、賃料収入を手にすることができることになって不合理であることは、直感的に理解することができます。
最高裁裁判所も判決(最高裁平成17年12月16日判決、判例時報1921号61頁)の中で、次のように述べています。
⑴ 原状回復義務について
「賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ」
⑵ 通常損耗と賃料との関係
「賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ,建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。」
⑶ 通常損耗が賃借人負担となる場合の要件
「そうすると,建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。」
このように、最高裁は、通常損耗に関しては、賃借人は、原則としてこれを回復する義務を負わないとしています。原状回復義務に関するこのような考え方は一般的で、学説上も異論をみないと言われています。
3 通常損耗補修特約
ここで注目すべきは上記の⑶の部分です。最高裁は、原則として通常損耗につき賃借人は回復義務を負わないとしましたが、一定の要件が満たされる場合には、賃借人が通常損耗部分についても回復義務を負う場合がありうることを否定しませんでした。その要件としてあげられているのは、
「通常損耗にかかる修理費用を賃借人が負担する旨の特約(通常損耗補修特約)が明確に合意されていること」
であり、その明確な合意があったといえるためには、
① 通常損耗の範囲が賃貸借契約書上で明記されている
か、そうでない場合には
② 賃貸人が口頭で説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意のないようとしたものと認められること
というものです。要件としてはかなり厳格なものだと言えます。しかし、逆に言えば、この要件が満たされる場合には、賃借人が通常損耗の修理費用を負担しなければならないとされる場合がありうるということを意味します。
ただし、最高裁は「少なくとも」上記の要件が必要と述べているだけですので、この要件を満たしたからといって、通常損耗補修特約の有効性が常に肯定されるわけではないということに注意が必要です。
4 原状回復をめぐるトラブルの状況
敷金や原状回復をめぐるトラブルは今に始まったことではありません。賃借人は通常損耗については回復義務を負わないということも昔から言われていたことです。しかし、今なぜ敷金返還をめぐるトラブルが増えているのでしょうか。
賃借人には通常損耗に関する回復義務を負わないとはいいつつも、市販の賃貸借契約書の多くには賃借人に対して修繕義務や過大な原状回復義務を負うとの内容の条項が書かれていました。しかし、それにも関わらず訴訟にまでなることはなかなかありませんでした。それは、請求額が必ずしも高額ではないこと、訴訟で敷金を請求するのは知識、費用及び労力が必要となること、賃借人が仲介をした不動産仲介業者の協力を得ることは難しく賃貸人・賃借人間で情報や交渉力の格差があること、世の中の賃借人間で協力、連帯をしようにもその仕組みがなく困難であったこと、弁護士へのアクセスも容易でなかったという事情があったからです。
しかし、近時、新築賃貸物件が増加したこと、新規賃料が低下し、賃貸借契約終了後新たな賃借人が見つかるまでの期間が長くなったこと、清潔志向の高まり等の借家市場の変化により、賃貸人が補修、クリーニング、リフォーム等の費用を敷金から控除する事例でトラブルになる例が増えていると考えられます。特に、差入れている敷金額が高額である場合、敷引特約(敷引特約の問題については、別の機会に扱います。)の敷引率が高い場合で訴訟に発展する場合が増えていると言えるでしょう。
(中野星知)
この4月に入学や就職、転勤で、マンションやアパートなどの部屋を借りて新生活を始めた方も多いのではないでしょうか。部屋を借りようと不動産仲介業のお店に行くとたくさん物件の情報を見せてもらえますが、「賃料」や「仲介手数料」のほかに「敷金〇か月分」「礼金〇か月分」などと書かれていますね。
1 敷金と礼金の違い
敷金は、不動産の賃貸借契約をする際に、借り手(賃借人といいます。)から貸し手(賃貸人といいます。)に支払うお金の一種です。礼金もこの点では同じですが、礼金は賃貸人が受け取りっぱなしで返却することが予定されていません。これに対し、敷金は後に賃貸人から賃借人に返却することが予定されているところが、礼金と異なります。
敷金は、賃貸借契約が終了した後、賃借人が退去して明け渡した時に、その時点までに賃料の滞納がある場合や、賃借人の使い方が良くなくて壊してしまいその修繕費がかかる場合など、賃借人が賃貸人にさらに一定のお金を支払う必要がある場合に、賃貸人が敷金からその金額分を差し引き計算し、その残額を賃借人に返還するという方法で清算されます。
2 敷金と保証金
敷金ではなく、「保証金〇か月分」とされていることもあります。しかし、多くの場合、この「保証金」も明渡時に未払賃料等が差し引かれて残額を返還すると賃貸借契約書に書かれていますので、その場合にはこの保証金とは敷金のことだと考えて差し支えないでしょう。
3 敷金が支払われる理由
賃貸人は不動産を貸す、賃借人はこれを借りて使いその対価(お礼)として賃貸人にお金を支払う、というのが不動産の賃貸借契約です。不動産を借りるその対価としてその賃料が賃貸人に、契約を仲介してもらったお礼として仲介手数料が仲介業者に、それぞれ支払われます。しかし、さらにこれに加えて、賃借人から賃貸人に敷金が支払われるのはなぜでしょうか。
端的に言えば、敷金は、賃料等の支払いの担保であり、賃貸人側にそのニーズがあるからです。
例えばマンションの一室が賃貸された場合をイメージしてください。契約が終了して賃借人が退去する際、その時点で家賃の滞納が1か月分あったとします。賃貸人としては、敷金2か月分を契約時に受け取っていたのだとすれば、滞納の1か月分の家賃を差し引いて、残り1か月分を敷金返還として賃借人に清算することで、賃貸人は、滞納家賃を確実に回収することができます。もし、賃借人の部屋の使い方が乱雑で部屋の備品が壊れていた場合、その修理に費用がかかるとしてその修理費用相当額を差し引いて清算すれば、修理費用も賃借人に支払ってもらったことと同じことになります。
また、家賃の滞納が長期にわたる場合、賃貸人としては賃借人に退去してもらって別の人にまた賃貸したいと考えるでしょうが、その賃借人が退去を拒む、あるいは退去できない場合(家賃を長期にわたって滞納する人は経済的に余裕が無く、引っ越したくてもすぐには引っ越すことができない場合が多い)、最終的には明渡訴訟をして判決をもらい、強制執行の手続きによることになりますが、それには相当な時間がかかります。その間も家賃の滞納が積み重なりますが、敷金をあらかじめ多めに受け取っておくことによって、仮にその敷金で滞納賃料の全部をまかなえないとしても、その分、損害が少なくて済みます。
4 敷金の定義
意外なことですが、民法には敷金契約に関する規定がありません。
先取特権に関する316条第1項に、「賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」、賃貸借の更新に関する619条第2項に「従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。」と敷金という文言が出てくるのですが、肝心の敷金というものが何なのかが分かる規定は見当たりません。
もっとも、講学上、敷金は次のように説明されています。
敷金とは、
① 賃借人の賃料債務その他の債務を担保する目的で、
② 賃貸借契約が終了して目的物を返還したときに賃借人の賃貸人に対する未履行債務があればその額を差し引いた残額を返還するという約定の下、
③ 賃借人から賃貸人に交付される金銭
をいう。
したがって、このような性質を有しているものは、契約書にそのものズバリ「敷金」と書かれていても、「保証金」と書かれていても、あるいはそれ以外の名称がつけられていても、講学上の敷金にあたり、敷金契約の解釈論があてはまると考えられます。
5 敷金をめぐるトラブル
敷金は、不動産賃貸借契約が一般に多く行われる中で慣習的に成立したもので、その仕組み自体はとても合理性があるのですが、実際に賃借人が退去した際に具体的にいくらが返還されるべきなのか、契約書上退去時には一定額は返還しないとあらかじめ書かれている場合(敷引特約といいます)にその特約がどこまで有効なのか、などをめぐってトラブルが絶えません。
この敷金をめぐるトラブルについて、次回以降、少し触れてみたいと思います。
(中野星知)